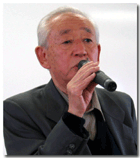
世界人権宣言大阪連絡会議は、2004年1月26日、「不可触民と現代インド」(光文社新書)を執筆された山際素男さんをゲストに第247回国際人権規約連続学習会を開催しました。報告要旨は以下の通りです。(文責 事務局)
インドとの出会い
私とインドとの関わりは1959年にインドへ留学したことから始まりました。
私がインドに行き、まず一番驚いたのは日本の研究者や学者が書いたインドに関する本と、現実のインドとの違いでした。こういったインドの紹介の仕方というのは今でもほとんど変わっていません。だから日本人がそういった本から知るインドと、私が見続けてきたインドとの落差は非常に甚だしいものがあります。例えば、当時はインドの歴史や社会について書かれているどんなに厚い本でも、インドには不可触民という人々がいて、それはどういう人々なのかということをきちんと書いていた本は1冊もありませんでした。だから私は自分が留学するまで、インドが不可触民というすさまじい差別の中を3000年生き続けている人々がいる国であるという概念すら持ちえていなかったのです。
そんな私もインドで一応大学生としての生活を始めることになりました。しかしインドの大学には上層階級の人々が多く、特権階級の住処となっていた。そのため私が不可触民の人と初めて出会ったのはある事故によってでした。
不可触民との出会い
私がビハール州のパトナの大学に籍を置いていた時、ある場所へインド人に連れられて写真を撮りに行ったときのことでした。その移動中に朝早く畑の中を車で走っていたのですが、そのときに車の前を横切った農民を跳ね飛ばしてしまったのです。恐らくその農民は即死だったと思います。私は当然そのときすぐに車を止めるものだと思っていましたが、運転手はひき逃げをしたのです。
私は止まるように何度も言ったのですが、同乗のインド人に「ここで止まってどうするんだ、俺たちがどうなるのか分かっているのか」と言われるとそれ以上何も言えなくなってしまいました。しかしこれだけ悪質なひき逃げ事件にもかかわらず警察に調べられたり、新聞で報道されることはありませんでした。そこで困り果てて周囲に相談すると帰ってきた答えは異口同音に、「どうせ相手は不可触民なのだから放っておけ」というものでした。
このとき初めて私は不可触民という言葉を聞き、こういった隔絶した社会があることを初めて知らされたのです。結局、私もそれ以上追及するのをやめてしまいました。なぜならインドの社会で不可触民問題はタブーに近かったからです。それ以後も不可触民の人々の姿を目にすることはありましたが、彼らの存在が社会的にどういうものなのかについてはそれから10年以上も全く追求することはなかったのです。
その後、私は日本に帰国していましたが、ある事件をきっかけに再びインドへ行くことになったのです。1975年に初代首相ネールの娘であるインデラ・ガンジーが首相の座を追われ、インドは政治的に混乱していました。(後に彼女は選挙に打って出たのだが結局大敗してしまい、インド独立以降続いた国民会議派政権からシュードラ階層の有力政治家が率いるジャナタ党に政権を譲ることになった)。
つまり国民会議派は自分たちの下の階層の政党に政権を握られてしまい、その主役となったのがインドの民衆であるなどという情報が私にも届いてきたのです。あのひき逃げされても何も言えなかった人々までもがインデラ・ガンジーを倒せと立ち上がったという事実を聞き、私は居ても立ってもいられなくなり再びインドへ出かけました。これが今日の指定カースト民(元不可触民)を含めた新しいインド社会の変動との出会いでした。
カースト制度の実態
インドにはヒンズー教・ブラーミン階級が作ったカースト制度という四姓制度があります。一番上がブラーミンという僧侶・司祭階級で、次が王族・戦士族のクシャトリヤ、三番目がヴァイシャという商人階級、そして最後の四番目がシュードラという奴隷としての労働者・農民階級で構成されています。このようにそれぞれのカーストによって職業が決められていることがカースト制度の特徴だといえます。
つまりインドのヒンズー人口の約55%を占めるシュードラが、上位の3カーストに奉仕する階層であることが定められていて、実際にはこの人々がインドの基本的な社会的機能を支えているのです。これがインドのカースト制度ですが、実はこの下にアティシュードラ(シュードラ以下の階層)という階層があって、日本語では不可触民と呼ばれています。
これまでインド政府は不可触民が占める割合は人口の22~23%としていましたが、実際には30~35%が不可触民であることが分かってきました。つまり政府の統計には出てこない多くの人々が不可触民として位置づけられており、それらの実態も日本では紹介されていません。
語られることのない不可触民の歴史
カーストという言葉はヨーロッパ人の言葉で、インド人は、普通ジャーティと呼んでいます。このジャーティという言葉には元々「生まれた場所」という意味があり、自分が属する集団・土地から来ている言葉です。従ってカースト制では4つの階層と不可触民に分けられていますが、実際インド人が古代から続けている生活形態ではそれぞれの民族・種族・部族に加えて、それぞれが属する村・土地・職業といった千差万別のジャーティがあり、その数はインド社会の多様化に併せて増え続け、現在では数えられるだけで6000あるといわれています。このような帰属意識の強いジャーティ意識がインドのカースト制度が変わらない大きな原因の一つになっているのです。
紀元前1500年頃に西ユーラシアから来た白人種がインドを支配するために以前からあったジャーティ意識を、ブラーミンを頂点とするカースト制に整理して、秩序化しました。これが今日のカースト制度の歴史です。このような歴史の中でシュードラ以下の人々は、これまで3000年に渡って搾取され、そして学ぶ機会を徹底的に奪われ続けてきました。
その結果彼らは神と同等の地位にあるブラーミンと自分たちを比較する知識、あるいは自分たちが置かれている境遇に疑問を抱く動機や能力までも奪われてしまっているのです。またヴェーダなどヒンズー聖典の知識はブラーミンに独占され、クシャトリヤやヴァイシャは学ぶことは許されていましたが、人に教えることは許されていませんでした。そのために最高教育機関である大学はブラーミンに独り占めされてしまい、そこで学ぶ者は全てブラーミンの文献や考え方を学ぶことになります。
当然日本の研究家もそれを学んだのでしょうから、日本の書物に出てくるインド学というのはブラーミンの作り出したものばかりで、だからこそ不可触民に関する記述が出てこないのです。いずれにしてもこれがカースト制度の実態であるのですが、このようなインドにも変化が訪れています。
アンベードカルと不可触民解放運動
 インドで不可触民を中心とした社会変化の柱となったのが、アンベードカル博士という人物でした。彼は不可触民の出身で子どもの時から非常に厳しい差別を受けていましたが、彼の出身であるマハラシュトラ地方のある藩主がアンベードカルの天才を見出し、彼を欧米に留学させ、当時の世界最高学府で学問を身に付けさせました。そしてアンベードカルは政治、経済、法律、社会学といった様々な学問を学んでインドに戻り、藩主が用意した職に就くのですが、彼は差別によって住む家すら貸して貰えませんでした。結局彼は短期間で仕事を辞めざるをえず、ボンベイに戻り、ここから彼の不可触民解放運動が始まり、それがやがてインド全土に根付いていったのです。
インドで不可触民を中心とした社会変化の柱となったのが、アンベードカル博士という人物でした。彼は不可触民の出身で子どもの時から非常に厳しい差別を受けていましたが、彼の出身であるマハラシュトラ地方のある藩主がアンベードカルの天才を見出し、彼を欧米に留学させ、当時の世界最高学府で学問を身に付けさせました。そしてアンベードカルは政治、経済、法律、社会学といった様々な学問を学んでインドに戻り、藩主が用意した職に就くのですが、彼は差別によって住む家すら貸して貰えませんでした。結局彼は短期間で仕事を辞めざるをえず、ボンベイに戻り、ここから彼の不可触民解放運動が始まり、それがやがてインド全土に根付いていったのです。
この点からも、アンベードカルとその活動を学べばインドと日本の差別的な社会が有機的・具体的につながっていくだろうし、今燃え上がっている不可触民の姿は差別と闘っている日本人にとって大変な励ましになると私は確信しています。
アンベードカルは様々の活動以外にも亡くなる直前の1956年10月にヒンズー教から仏教に改宗したのですが、改宗したその年12月に新生インド憲法の草案作りの過労がたたったのでしょう、急死してしまいました。しかし56年に彼と一緒に仏教へ改宗した40万人の仏教徒が今日では1億人を超えるといわれています。アンベードカルの蒔いた種は大きく成長し、指定カースト(元不可触民)や仏教徒の大きな変革の意志はインド社会を揺るがす勢力の一つとして成長してきています。
アンベードカル以外にも不可触民の問題を何とかしなければいけないと考えるブラーミンの有力政治家・思想家は20世紀初頭からいましたが、彼らは上層カーストであるために結局は自分たちの不利益になることは何もできませんでした。ですから自らが不可触民出身としてその解放運動を全土的に広めていった最初の指導者はアンベードカルに他ならないといえます。
日本人仏教僧 佐々井秀嶺
最高の指導者であったアンベードカルを失って、彼と一緒に改宗した仏教徒たちは10年以上何をして良いか分からぬまま試行錯誤の時期を過ごしますが、そんな彼らの前にひょっこり現れたのが佐々井秀嶺という日本人の仏教僧でした。本人はアンベードカルの霊に呼ばれてインドにやってきたと言っていますが、彼はアンベードカルの意志を継いで今日インド仏教の大指導者になっています。
また昨年の3月からは宗教的マイノリティコミュニティー間の争いを調停する委員会の仏教徒代表として、インド政府から任命を受け活動しています。ところが日本の大教団はそんな彼の活動やインドの仏教徒に協力するどころか、インドの仏教徒と協力しようとする僧侶を教団から排斥している。これが日本の仏教界の実態なのです。
ガンジーとアンベードカル
日本ではマハトマ・ガンジーといえば偉大なインド独立の父として大変有名です。確かに彼がインドの独立に果たした功績はとても大きく、またその手法が平和主義的であったため、欧米で高く評価されているのも事実です。しかしそれはインド支配階層の手によって意図的に誇張されてしまい、いつしか「ガンジー神話」になってしまっているのではないでしょうか。
彼の残した功績は大きいのですが、私が始めてインドを訪れた当時は、公共の場でガンジーを批判することは法的に禁止されていたのです。これは逆にいえばそこまでして彼の権威を守ろうとする意図の現われであって、それを中心的に行ったのが当時の会議派政権でした。
つまり彼らは自分たちが作り上げた「ガンジー神話」を政権維持の宣伝材料にしていて、その点では日本の天皇制に通じるといえるでしょう。しかしそれでもアンベードカルは「ガンジーはインドのイギリスからの独立には貢献したが、不可触民のためには何もしなかった」と批判して、ガンジーと徹底的に対立してきました。
歴史的事実からも明らかですが、結局のところガンジーはインド社会をバラバラにしないために不可触民をそのままにしておくカースト制を望み、これに対してアンベードカルは、不可触民は分離・独立してでも平等を勝ち取らなければならないと考えていました。つまり日本にはガンジーが不可触民を解放したという誤った認識さえもがあるようですが、実際にそれをやったのはアンベードカルであって、ガンジーはアンベードカルの不可触民解放運動をつぶす存在として利用されたともいえます。
インドのカースト制には長く厳しい差別の歴史があり、日本にはその事実さえ正確に伝わっていないという問題もあります。しかしその中でも不可触民の人々は立ち上がろうとしているのです。だからこそ皆さんにそういう人々ともっと深いつながりを持ってもらいたいと願っており、それが皆さんの使命ではないかと思います。