第5章 学校における外国人児童生徒支援のあり方
―言語指導の側面から
櫻井千穂
私は、外国人児童生徒の言語教育に関して、母語、日本語の両言語の保持・育成の観点から、研究および現場での支援を行っている。
本日は、関西地域のA市をフィールドとして学校の先生方と一緒に行った日本語読解力調査(中間)について報告する。A市には、中国にルーツがある人々の集住地区があり、そこを校区とする小・中学校には、多くの中国帰国児童生徒が在籍している。そして、彼らの多くは、言葉の問題、アイデンティティの問題を抱えている。
1 日本の外国人児童生徒
①現状
今現在、学校で日本語指導が必要とされている外国人児童生徒は、文科省の「日本語指導が必要な外国人児童生徒の受け入れ状況等に関する調査」(1991年度から毎年実施)の中で、「日本語で日常会話が充分にできない児童生徒及び日常会話ができても、学年相当の学習言語が不足し、学習活動への参加に支障が生じており、日本語指導が必要な児童生徒」と定義されている。同平成20年度調査によれば、それに当てはまる児童生徒は2万8575人(2008年9月時点)である。この数は、前年と比較しても12.5%伸びており、毎年増加傾向にある。
ただ、現実に学習場面で困難を抱えている子どもの数はこの限りではないと言われている。学習活動への参加に支障が生じているかどうかの判断基準は、各学校、各担当者によって異なり、例えば、来日後3年以上の児童生徒をこの数に含めないという学校もある。また、様々な理由から学校に通えなくなった、いわゆる不就学の児童生徒の存在も忘れてはならない。
②これまでの外国人児童生徒支援の前提
これまでの外国人児童生徒支援の前提は、「日本語ができれば授業に参加ができる。在籍学級にいれば、自然と日本語が身につく。教科語彙を辞書で調べて訳し、こういうものだとわかれば、授業に参加できる」というものであった。日本語指導が必要だと判断された児童生徒には、「取り出し授業」といって、子どもをクラスから取り出して、日本の(学校)生活に適応するための指導や、日本語の初期指導、そして、補助的な教科指導も行われているのだが、そこでは、漢字や語彙、四則計算のプリント学習が中心であったり、従来型の英語教育で用いられてきた「文法訳読法」のように、文法を説明し、教材を母語に訳していくというやり方、または、国語の音読指導に偏ってしまうというところが多々あった。今でもそういう指導をされている現場は少なくはないだろう。
このように日本の現在の外国人児童生徒支援は、取り出し授業等の場において、生活適応指導や日本語の初期指導から、日本語による教科学習へとやっと目が向けられ始めたばかりであると言ってよい。文科省が推進してきた「JSLカリキュラム」という、在籍学級での活動に参加できるようになることを目的とした取り組みもなされてきてはいるが、本来児童生徒が多くの時間を過ごす在籍学級と日本語教室との連携や、在籍学級そのものの在り方、また児童生徒の母語や母文化の重要性については十分な議論がされているとは言いがたい。こうした「切り取られた文脈」の中での、一部の技能習得が目的となった日本語指導のあり方は検討を要すると考える。
2 世界の外国人児童生徒への支援の在り方
①外国人児童生徒の低学力傾向
ここで、一旦、世界の国々に目を向けてみたい。外国人児童生徒の問題がどういう形で取り組まれているかを紹介しよう。図1は、PISA(OECDが実施している学力調査)の2003年度調査の結果から、移民の子どもとネイティブ(その国(現地)の言葉を母語とする)の子どもの読解力を比較したものである。上から順番に国の名前が掲載されていて、左にグラフが伸びれば伸びるほど、移民の子どもたちとネイティブの子どもとの読解力の差が大きいということを表している。
図1を見ると、ほとんどの国で移民の子どもとネイティブの子どもの読解力の間に差があることがわかる。一世、つまり、学齢期途中で移動してきた子どもたちが、その国の言語でのテストに十分なパフォーマンスを示すことができなかったということは想定できる。しかし、それだけではなく、二世、つまり、現地生まれの移民の子どもたち(たとえば、アメリカで生まれたスペイン語母語の子どもたち)が、ネイティブの子どもたちと比べて、読解力が有意に低いという結果が出ているのである。
言い換えれば、学齢期の初めから、その国の教育を受けている移民の子どもたちですら、学習環境にハンデを抱えているということになる。この結果は、親の教育的・社会的・経済的社会背景を排除した後も、有意差が残る。やはり、二言語環境・第二言語環境の中で育つということが学力にどういった影響を及ぼすのかということがわかる一つの大規模な調査だと言える。
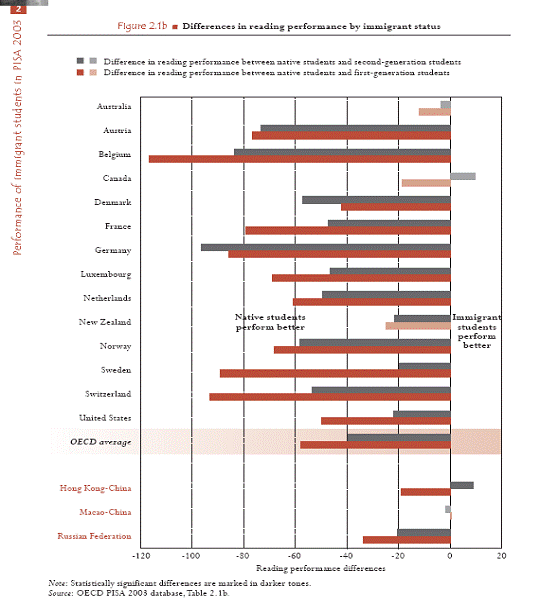
図1 移民の子どもの読解力
次に、別の調査を紹介したい。アメリカの英語学習児童生徒の調査を行っているバトラー(2008)からの引用である。アメリカでは、就学している幼稚園から高校生までの児童生徒総数約4700万人のうち10%(約500万人)が英語学習者である。そのうちの3分の1がカルフォルニアに住んでいて、小学生の約半分が英語学習者=移民の子どもたちである。そして、そのうちの8割がスペイン語話者となっている。
それでは、この子どもたちの高校卒業後の進路はどうなっているのか。
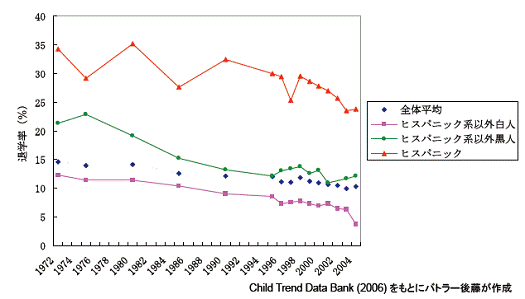
図2 ヒスパニック系の高校卒業以前の中退率(バトラー後藤2008より)
図2が示すように、1番上の線がスペイン語を母語とする子どもたちの中退率で、だいたい30-35%あたりを推移している。近年、減少傾向にあるようだが、それでも、25%、4人に1人が高校中退しているというわけである。ヒスパニック系以外の白人は一番下の線である。1970年には約10%、10-9人に1人という割合であるが、それが2004年になると、5%まで下がってきている。20人に1人の割合であり、ヒスパニック系と比較すると、大きな差があると言えるのではないだろうか。この結果は、中退率と子どもたちの言語・生活環境がどれだけ関わっているのかを示した、一つの大きな調査であると言えるだろう。
さらに別の調査、トーマス&コリア(2002)の調査を紹介したい。アメリカの5つの州で実施され、延べ21万データを使用した大規模調査である。幼稚園から高校生までのマイノリティ言語(言語少数派)の子どもたち、つまり、移民の子どもたちと、英語を母語とする子どもたちの学力、言語能力の差について調べたものである。
様々な角度からの調査が行われているのだが、ここで結論として言われていることは、先ほどの日本の外国人児童支援の前提として捉えられてきたことと全く反対の内容である。「在籍学級で自然と日本語が身につく」のでなく、在籍学級(メインストリームクラス)だけで学習した、英語を第二言語とする子どもたちは、バイリンガル教育やESL(取り出し授業・在籍学級に入る前に英語を勉強するクラス)のコースを受けた子どもたちに比べて、小学校5年生までに「読み」と「算数」でついていけなくなるケースが大変多いことが明らかになっている。さらに、この在籍学級のみで勉強した子どもたちのドロップアウト率が一番高いのである。
加えて、バイリンガル教育では常識だと言われていることだが、該当学年相当の第二言語レベルに到達するまでには、少なくとも4年が必要だと、この調査の結果は示している。カナダのカミンズは最低でも5年から7年と言っているし、小さい子になればなるほどその年数がかかるとも言われている。8-9歳に分水嶺があると言われていて、8-9歳以下で来た子どもたちというのは、その同じ年齢の子どもたちと同じ学力に追いつくまで、7年から10年かかるという調査もある。その年齢以降で来た子どもたちでも、5年から7年かかるわけであり、学校に在籍している間中ずっとかからなければ、ネイティブの子どもたちに追いつくことができないのである。
②バイリンガル教育の意義
では、そういった子どもたちをどういう方法で支援すればいいのだろうか。このトーマス&コリア(2002)の調査によれば、唯一効果のある支援は、バイリンガルプログラムだけだったのである。バイリンガルプログラムというのは、彼・彼女らの母語も伸ばすし、第二言語も伸ばす。その割合によってプログラムの名前もかわってくるので、ここで詳細を述べることは避けるが、例をあげるなら、半分の教科を母語で、残りの半分の教科を第二言語で教えるといった方法である。
先ほどのPISA調査では、カナダと香港だけが、移民の子どもたちの学力がネイティブの子どもたちより優っているといった結果が出た。そのカナダは、バイリンガル教育が盛んであり、移民の子どもたちの母語を保障しようという意識が非常に高い国である。それ以外の国は、移民の子どもたちを30年以上受け入れているにもかかわらず、依然として移民の子どもたちの学力を現地のネイティブの子どもたちの学力に追いつくまでの教育はできていない。
今、日本はどちらを選択しようとしているのか非常に大きな岐路に立っている。日本はアメリカやカナダのように大規模な移民受け入れを行っているわけではない。先ほども述べたように、現在では、日本語指導が必要だとされている児童生徒は、数値としては2万8000人ほどである。しかし、その厳しい環境下にいる子どもたち一人一人に対しどのような教育的支援を行うかという視点は、普遍的な教育観にも通ずる重要な課題であると考える。近年、母語の大切さは色々なところで話されるようになってきたし、特にO県では、母語教育、アイデンティティ教育、母文化の教育というものを非常に重要視し、母語も含めて子どもたちの人権をどうしていこうかという空気が根付いている。そして諸外国での調査を見ていると、やはり母文化、母語、アイデンティティの教育を重要視してやっていく以外に、子どもを救う道はないと思われる。
3 日本における外国人児童の日本語読解力調査(中間報告)
日本の場合、外国人児童生徒の言語能力の実態調査は少なく、特に学力の基礎であるとも言われている読解力調査はほとんど行われてはいないという状況である。しかし、外国人児童生徒にとって有益な支援を考える上で、実態を把握するための基礎的研究は必要不可欠である。
しかし、そもそも日本国内にいる外国人児童生徒数はその総数が少なく、さらにその子どもたちの約8割が5000校以上の公立の小中学校に、一つの学校に5人未満といった状況で点在している。それらの学校を全部回って、言語状況の調査をするのはほぼ不可能に等しい。また、個人情報や人権問題と深く関わってくるので、日本語教育研究の研究者たちも調査の必要性を感じてはいるが、なかなか調査がしにくい側面がある。
①「デベロプメンタル・リーディング・アセスメント・ジャパニーズ」による調査
A市で外国人児童生徒の支援プログラム作りをするうえで、子どもたちの日本語の読解力の状態を知り、より有益な支援をしようということで、2007~08年にかけて日本語読解力・読書力の調査を実施した。たくさんの先生方と保護者の方の協力を得て、中国にルーツのある児童88名の読解力・読書力がどのように育っているのかという点を調べた。
調査はペーパー式ではなく、1対1の面接式のテストで、一人の児童に1時間かけて行うといったものである。本日の報告は、そのうち日本生まれの中国にルーツのある児童63名(CNS:Chinese Native Studentsのグループ)の結果と、対象群として実施した同じ小学校に通う日本語母語の子どもたち36人(JNS:Japanese Native Studentsのグループ)の結果から、日本語読解力・読書力がどのように育っているのかを比較していきたい。日本生まれの中国にルーツをもつ子どもたちに限ったのは、日本で生まれて、日本語を母語とする子どもたちと同じように保育園・幼稚園に通い、同じ小学校で学ぶという、教育的環境が似通った条件での比較ができればという考えからである。一軒一軒の家庭の経済的環境については、今回の調査に含めてはいないが、A市全体の特徴としてはある程度コントロールされているのではないかと考えた。では、何が大きく違うかというと、CNSグループの家庭での言語、つまり、両親の話すことばが中国語であるという点である。CNSグループの保護者の言語能力に関して、具体的な調査をしてはいないが、子どもたちへのインタビューの中で、両親同士の会話が中国語でなされるということ、保護者が日本語はあまり話さないということが確認されている。
読解力・読書力テストには、「Developmental Reading Assessment‐Japanese」(ニューインターナショナルスクール開発)を利用した。レベル分けされたテキストが47あり(幼稚園から中学2年生までに対応しており、さらに開発中)、読解力・読書力の発達段階をずっと見ていくもので、国語のテストとは全く違うものである。本調査では、各学年、年齢において、1-2冊(低学年では2冊、高学年では1冊)、レベル分けがはっきりしたテキストのみを使用した。まず学年レベルにあったテキストを子どもに渡す。事前の会話力のテストでもう少しできそうなら、学年より一つ上のテキストを渡す。もし内容が難しくて理解できないと子ども自身が判断したら、テキストレベルを一つ下げ、逆に、最後まで読みきれると判断すれば、そのテキストで進める、という方式である。子ども自身が、挑戦できる(したい)もしくは、自分に合っていると思えるレベルのテキストを読む。つまり、本人にテキストレベルの決定権を委ねるのである。このやり方は主観的で揺れがあるように見えるが、テストを重ねていくと、子どもたちの主観がどれだけ大事かということに気が付く。子どもが一番できたと思うレベル、そして一番自分が読めると感じたレベルがどれなのかということを知るには、この方法しかない。音読チェックだと、速く読めても内容を理解できていないとか、遅く読んでもよく内容を理解しているということが起こる。理解できているのに、読む速度が「遅い」という理由でテキストレベルを下げられると、子どもにとっては心外であろうし、逆に、わからないものを周りから客観的に読めそうだと判断されて、読み進めることは苦痛であろう。それゆえ、このテストのテキストレベルの選択は子どもの目線に立ったものだと言える。
一つのテキストを最後まで読ませ、読んだ後に「このお話を始めて聞く人にわかるように話してください、全部終ったら、「終わり」と言ってください。」と再話(retailing)をするように促す。そのあとに、テスターは、子どもが口にした情報をもとに、質問を行っていく。それぞれのテキストに基本となる質問は用意されていて、それを基に質問をするのだが、ここで気をつけるべきことは、テスターが子どもに新情報を与えずに、子どもの発話内容につなげていって、子どもの理解の一番深いポイントを探る、ということである。測るのは、予測力・推測力・音読の正確度・流暢度、内容の理解度、読み行動(絵を手がかりにしているのか、文字を一字一字押えながら読んでいるか等)、語彙の概念がどれだけ育っているのか、また読書習慣に関するインタビューも同時に行う。さらに高学年は、要約力、読解ストラテジーといって、読むときに登場人物の気持ちを想像しながら読んでいるか、先を推測しながら読んでいるか、自分の中で要旨を組み立てて読んでいるかなどについても、インタビューだけではなく、書くタスクによって調べる。
評価は、以下のような方法で行う。まず、1人の児童の1時間の音声データを全部聞きなおして、全発話を文字化する。こうすることで、子どものつまずきなどが詳しく見えてくる。次に、それを観察ガイドDRA読解力評価表にそって、採点する。
読解力評価項目については、4年生までと5年生以上とでは少し異なる。4年生までは事実の理解、場面の描写、解釈、それから動作主がわかっているかどうか、教師がどれだけ質問を繰り返さないといけなかったか、その教師の誘いかけに対してどんな質で応答ができたのかが評価項目として挙がっている。5、6年は予測力、要約力、事実関係の理解、解釈、解釈の根拠、メタ認知(読書ストラテジー)、音読の表現力、区切り方、速度、正確度に加え、読書習慣に関するもので、読書の範囲(ジャンル)、自己評価と目標設定力を点数化する。それぞれの項目を1-4点のリッカート式で採点し、判断する。これを学校の先生と2人で採点を行い、評価の信頼性を検討した。この結果と、読書習慣に関するインタビューの結果から環境と読書力・読解力との関係についての考察を試みた。
②調査結果の概要
それでは、調査結果について見ていくことにしよう。
表1のテキストレベルの表の見方を説明しておこう。左端の一番上「1CNS」というのが、1年生の「Chinese native students 」、つまり、中国語母語児童である。その下が「1JNS」で、1年生の日本語母語児童である。その人数が、それぞれ11人、6人となる。1CNSを横に見ていくと、「C8」「D1」と記載している。ABCDは判定のレベルを表している。「A」判定は「高度な理解」、在籍学級で先生が見て、「この子よくできるなあ」というレベルである。「B」判定は「適度な理解」、これも普通にクラスにいて問題のない範囲である。「C」判定は「ある程度の理解」、これは在籍学級でそのテキストが扱われた場合に、様々な足場かけがあれば、なんとか参加ができるというレベルである。「D」判定は「ほとんど理解していない」、そのテキストを扱った授業への参加は非常に厳しいというレベルである。
表1 テキストレベルの結果
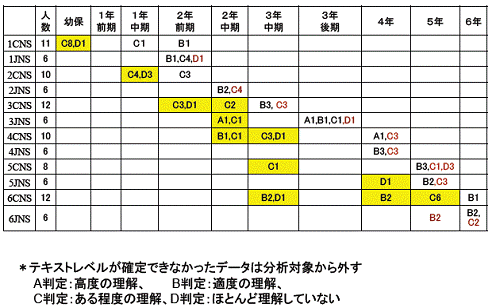
左上端の「C8」というのは、幼稚園・保育園レベルのテキストを読んで「C」判定を受けた子どもが8名、そして、「D1」というのは「D」判定を受けた子どもが1名いたということである。加えて、1年生中期のレベルのテキストを読んで、「C」判定を受けた子どもが1名、さらに、2年生前期レベルのテキストを「B」判定で読んだ子どもが1名いたというわけである。つまり、11名のうち、この「B」判定の子どもだけは、在籍学級の授業に問題なく参加できるレベルの読解力・読書力がある、ということを示している。幼稚園・保育園レベルの本を読んで、「C」判定「D」判定の9人というのは、在籍学級でやっていくのがかなり厳しいという状況である。
再話データを見ると、いろいろと興味深いことがわかる。少しだけ例をあげてみよう。小学3年生のJNSの再話の例だが、「森の少女ブーラン・クニン」という25ページくらいの小学校3年生後半レベルのテキストを読んだ時のものである。その児童はA判定の結果を得たのだが、まるでテキスト1冊を丸暗記でもしたかのように、10数分かけて、細部に至るまで詳細な再話をしてくれた。
一方で、同じ学年で同じクラスのCNSの再話の例であるが、「きつねとぶどう」という小学校2年生前半レベルの本を読んで「C」判定を受けた。自分で、段落を構成しながら話すということをしないため、必然的にテスターが先を促す質問をするのだが、それにも一問一答式で答え、単語、単文レベルの発話がほとんどである。もちろん、CNSグループに属する全ての子どもがこのような型を示すわけではないが、傾向として、CNSグループの子どもたちの1~3年生に非常に多かった。
この子どもたちは、毎日の生活において頻繁に使用される簡単な単語や単文だけのやり取りだけでやり過ごすことができる日常会話の中では、日本語を母語とする子どもたちと比較しても、全く遜色のない日本語を話す。普段話す様子を見ているだけではどこにルーツがあるかさえわからない。しかし、こうやって本を読んで、その内容を自分の頭の中で再度組み立て、「再話」という形で表現するという活動においては、豊かな言語環境の中にいる子とそうではない子の間に、歴然とした差が出てくるのである。もちろん、日本語を母語とする子どもの中にも同じように十分な再話ができない子どももいるが、割合が違うのである。
表2 小学校3年生の再話例
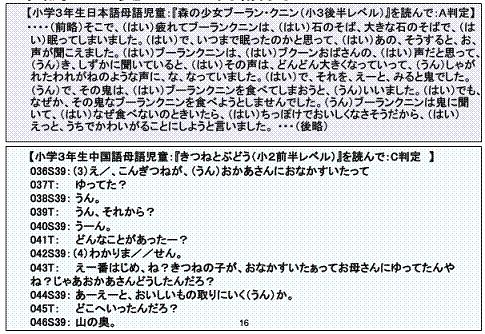
以上の結果から、それぞれの在籍学級の授業に参加するために特別な支援が必要だと思われる子どもの割合は、CNSグループでは、1年生、80%以上であった。そして、2年生は70%、3年生は50%、4年生は約60%、5年生約50%、6年生が約90%という結果が出た。一方で、JNSグループでは、1年生で10%、2年生は1人もいなかった。3年生は50%、4年生は0%、5年生は20%程度、6年生は0%という結果であった。割合的にCNSグループの子どもたちの読解力の方が低いということがわかる。
また、音読の流暢度について見てみても、①文字の拾い読みの段階、②拾い読みと文節読みの段階、③文節読みの段階、④文節読みと文レベルの段階、⑤文レベルの読みの段階、というように分けると、CNSグループは1年生の半分が①文字の拾い読みの段階であった。また、CNSグループの3年生の3割が②拾い読みと文節読みの段階であった。それに対し、JNSグループは、1年生の3割
が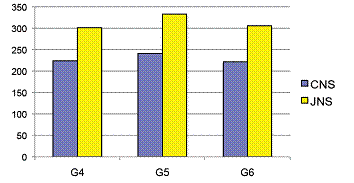 ②拾い読みと文節読みの段階 図3 音読速度の比較(1分間に読んだ音節数の平均値) ②拾い読みと文節読みの段階 図3 音読速度の比較(1分間に読んだ音節数の平均値)
にあるだけで、1年生の残りと、他の学年の子どもたちのほとんどが④文節読みと文レベルの段階、⑤文レベルの読みの段階にあった。
次に、4、5、6年生で同じテキストを読んだ子どもたちが1分間に何音節読めるのかという平均値を出した(図3)。これを見ると、差が見て取れる(未統計処理)。4年生は1分間で77音節、CNSグループの方が少ない。5年生は91音節、6年生は83.2音節の差があり、JNSグループの方が音読速度ははるかに速い。これは、漢字の読みの躓きによる音読速度の低下の要因を排除した上での結果である。北米での移民の子どもたちの読みの速度に関する調査からも、母語以外の言語での音読速度においては、ネイティブの子どもと比較して有意な差があるということが明らかになっている。
CNSの6年生の9割が要支援という結果を先に述べたが、漢字の識別と漢字以外の語彙量が少ないことによる語彙でのつまずき、そのため音読の速度が遅くなってしまい、そのテキストレベルを読むことが難しく、さらに、内容が理解できないため、テキストレベルを下げるということが起こっていたのである。
また、CNSの1年生は、拾い読みの段階である。小学校に入学してからひらがなを習う子どもが多い。保育園でもやっているはずだが、家庭では定着していない。よって彼らのほとんどは小学校に入学してから文字を覚えている。一方で、JNSの子どもたちの8割以上が幼稚園・保育園に行っている間に、文字を覚えただけではなく、絵本が読めるようになったと答えている。就学前教育がいかに大事かということを主張したい。
このように、文字の識別、語彙量の制限から、学年レベルの本を読む習慣がなかなか身につかない、本を読む習慣が身につかないがために、語彙量が増えないという悪循環が生じている。現在、学校教育現場では、読み聞かせの時間があったり、朝読書の時間があったりするが、子どもたちの本の選択や読み方を指導するところまでは至っていない。子どもたちは読書の時間に自分で本を選ぶのだが、読書に親しんでいない子どもの中には、例えば、4年生になってもずっと「ネズミ君のチョッキ」(幼稚園レベルの絵本)を好んで読んでいる子がいるのも事実である。片や、読書習慣の身についている子どもは4年生で、歴史の本や伝記の本、小説などを読んでいたりする。高学年になってくると、図4にあるように、4年生以上で学年レベルの本を読む習慣が、JNSグループは比較的ついてきていると言えるが、CNSグループの中にはその習慣がない子どもが多く、横ばいの状態となっていることがわかる。
最後の結果は、一番興味深いと感じたところである(図5)。読解力と家庭環境の関係を
 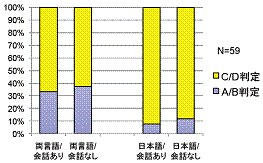
図4 学年レベルの本を読む習慣 図5 読解力と家庭での言語環境の関係
見てみたところ、家で児童が中国語を話していると、日本語の読解力は同じかもしくは下がるのではないかと思っていたのであるが、決してそうではないという結果が出たのである。今回の調査で、保護者が家庭で話すのはほぼ中国語である。その中で、子どもが保護者に対して中国語を話す、話そうとする、中国語と日本語を話すと答えたグループにおいて、3割の子どもが今回の日本語の読解力テストでA、B判定をとった。それに対して、保護者に対して日本語のみで話すと答えたグループは1割がA、B判定であった。つまり、家庭で日本語しか話さないと答えた子どものグループのほうが、相対的に日本語の読解力が低いという結果が出たのである。
これをどう解釈するかといった問題があるが、家庭での言語環境の質と量が、読解力を規定するようになるのではないかと考えている。日本語で話す方がいいか、母語で話す方がいいか、周囲の環境との関連があるため、一概には言い切れない。ただ、保護者と話す場合に、その保護者が自信を持って話せる母語を使って話す方が、必然的に会話の量は増えるだろうし、その質も高くなるのではないだろうか。こうしたことが日本語の読解力を高めている要因になっているのではないかと考えられる。
これらの結果をみると、家庭での保護者とのやり取りが非常に重要になってくるであろう低学年までの時期、特に、就学前の幼児教育は極めて重要であり、家庭で保護者が自信を持って語りかけられる言葉、つまり、母語による教育をしっかり進めていくべきではないかと考える。今回の調査で、JNSグループでは、小さいときに読み聞かせをしてもらった記憶があると答えた子どもがたくさんいた。しかし、残念ながら、CNSグループでは、家に中国語の本が一冊もないと答える子どもがほとんどであった。日本語の絵本等はあるようだが、保護者に読み聞かせをしてもらったと答えた子どもが非常に少なかったのである。
4 学校の中で望まれる支援体制
学校の中ではどのような支援体制が望まれるのだろうか。今回の調査から、言語環境が少なからず、子どもの読解力・読書力に影響を及ぼすと考えられる。実際、子どもは、言語を、経験を通して習得していくと言われている。語彙力が少ないのは、辞書を調べないから少ないのではなくて、経験値が少ないからなのである。それを考えると、ことばを介してのやり取りの量を増やし、質を上げるということが必要なのではないだろうか。日本語指導を切り取られた日本語授業の中で完結してしまっていても、実際に語彙力はついてこない。その代わり、周りとのやり取りを通して、経験の中でことばを学ぶことによって、そういった力がついてくる。新しいことばでも、既習知識と関連づけて、先にイメージを頭の中で作りだすことによって、スムーズに学ぶことができたりする。一つ興味深い例がある。学年は3年生だが、1年生の本がやっと読めるレベルの子どもに対して、3年生のテキストを学習する際に、語彙のレベルや文型をリライト(書き換え)によって下げ、それを家で読んでくるという宿題をだし、その後、毎日10~15分の再話活動をさせた。その後、本人の意向を聞きながら、テキストの原文を読ませてみると、「この本すごく簡単」と言うのである。原文に使われている語彙は難しいはずなのに、その前にリライト教材を読んで、物語の流れを把握し、イメージを持っていることが助けになって、わからない言葉も推測を働かせて読めているようなのである。後半の再話の中には、リライト教材では扱っていなかった原文の難易度の高い語彙が現れてくるようになったのである。
こうした教師と児童生徒のやり取りが大切なのはもちろんだが、子どもたち同士のやり取りも大変重要である。周囲とのやり取りが、子どもの最大限の認知活動につながることが重要である。従来から行われている、教師が主導で知識をどれだけ入れ込むかといったやり方だけではなく、子どもたちが自ら考え、答えを導き出せるように、周囲がサポートすることが必要である。
さらに、ことばと一見関係がないようで、一番関係があるのが自尊感情である。今回の調査を通して感じたことは、自尊感情が乏しい子どもが非常に多いということである。自分はできない、勉強が嫌いという子。通常なら、そんな子どもたちが1時間もかかるインタビューテストに集中して取り組めるはずがない、と思われるかもしれない。しかし、実際はそうではなかったのである。「勉強が嫌い」と口にする子どもであっても、子どもが話し始めるまで待ち、子どもの話にじっくり耳を傾け、その答えを肯定的に聞いていると、あきらめず、自分のことばで自分の考えを話してくれたのである。ほぼ例外なく、すべての子どもが自分自身の最大限の力を出そうとしてくれたのだ。「勉強が嫌い」と言ってしまうのは、そう言わざるを得ない環境があるからではないだろうか。取り組む前にあきらめざるを得ない環境があるからではないだろうか。自尊感情、自分のことを好きだと思える環境、取り組む課題を面白いと思える環境がなければ、何事にも前向きに取り組んでいくことなどできないのではないかと思う。
外国人児童生徒は、自分のルーツとは違う日本語の環境の中で、日本語を母語とし、日本文化を母文化とする子どもたちと同じ土俵の上で学習していかなければならない。そのハンデの中で、できるようになるよりも先に、「できない」 という劣等感が蓄積されていってしまう。しかし、見方を変えれば、彼らには、日本語、日本文化のほかに、母語や母文化と呼べるものが確かにある(あった)はずなのである。そのルーツをなかったものとして扱ったり、あってもまずは目先の日本語を、と指導するのではなく、その母語や母文化を「財産」と捉え、一番に大切にしていかなければならないのではないだろうか。母語・母文化という確固たるルーツの上に、日本語・日本文化を加えていくことで、二言語環境に生きることがマイナスではなく、プラスとなり得るのである。そして、それが自尊感情につながるのではないだろうか。
学校現場の中で指導・支援に携わる教師は、自分が受け持つ1~2年の間、日本語教室といった切り取られた文脈の中で日本語をいかに指導するということだけに着目していては、どうしても子どもたちが抱える背景、問題の本質が見えてこない。子どもたちの全人的発達を目指して教育に取り組む姿勢が大切だと考える。
参考文献
・生田裕子、2002、「ブラジル人中学生の第1言語能力と第2言語能力の関係―作文のタスクを通して」『世界の日本語教育』12号pp.63-77 国際交流基金日本語国際センター
・OECD編著、斉藤里美監訳、2007、『移民の子どもと学力―社会的背景が学習にどんな影響を与えるのか―』明石書店
・中島和子、ロザス・ヌナス、2001、「日本語獲得と継承語喪失のダイナミックス―日本の小・中学校のポルトガル語話者の実態を踏まえて」
・中島和子、2005、「バイリンガル育成と2言語相互依存性」『第二言語としての日本語の習得研究』第8号pp.135-166 第二言語習得研究会
・中島和子、2006、「学校教育の中でバイリンガル読書力を育てる―New International SchoolにおけるDRA-J読書力テストの開発を通して」『母語・継承語・バイリンガル教育(MHB)研究』2号pp.1-31母語・継承語・バイリンガル教育(MHB)研究会
・バトラー後藤裕子、2008、『外国人児童生徒教育の課題米国の経験を踏まえて』、母語・継承語・バイリンガル教育(MHB)研究会2008年度大会口頭発表資料
・文部科学省、2007、「日本語指導が必要な外国人児童生徒の受け入れ状況等に関する調査(平成18年度)」
|