第7章 学力格差と社会的背景
志水宏吉
1 はじめに -教育社会学の伝統
私はこれまで、教育社会学という学問を専門として研究してきた。私が大学院に入った28年前は、教育学や教育哲学、教育法法学、教育心理学などがメジャーで、教育社会学はマイナーな位置づけであった。しかし、ここ10年くらいは日本の教育界でも存在感が増し、現在では教育社会学者の発言や仕事が教育学のなかで紹介されることが増えてきた。
もともと教育社会学は「社会と教育の関係を考える」ということをやってきた。さらに具体的に言うと、「社会階層と教育との関係を考える」ということになる。社会学では「階層」というものを最も中心的なグループの概念として扱う。ヨーロッパでは「階級」概念が主流であるが、アメリカは所得階層というのが一番中心で、日本の場合は、議論はあるが「職業階層」と「学歴階層」が中心的に考えられている。諸外国に比べると、戦後の日本は、特に学歴が重視される度合いが相対的に強い傾向もある。いずれにしろ、教育社会学は「階層と教育」の問題をずっと扱ってきたのである。
それに加えて、我々のグループは「効果のある学校」研究を行ってきた。これにも実は源流がある。それは、1960年代後半から70年代のアメリカに求められる。『コールマン報告』とジェンクスの『不平等』という2つの書物である。そこでは、「学校は無力である。社会的不平等に対してあまり力がない」ということが実証的に主張されている。どこの国でも戦後社会を作っていくときに、学校教育を普及させるため学校を作り、そうすれば社会が良くなり民主化するという方向性でやってきた。しかし、1950~60年代を通じて、アメリカや日本を中心に教育が大衆化してきたにもかかわらず、世の中はあまり良くなっていないということが見えてきた。そこでアメリカ政府が莫大な資金をかけて調査を実施したが、その成果が、上記の2冊である。そこで、教育だけでなく福祉に力を入れなければならないという流れが生まれてきた。かつてジェンクスは、単純化して言えば、学力の4分の3は家庭環境により、学校の影響は4分の1だけであると結論づけた。そして、学力を規定する半分以上は学校以外の要因による、というのは今でも通説となっている。
ヨーロッパではイギリスのバーンスティンやフランスのブルデューが有名だが、「文化的再生産論」という考え方が主流を占めていた。どんな考え方かというと、「学校では見かけ上は、社会的不平等を減らせる、また社会の不平等構造を改善するということが語られているが、実際は、支配層による支配を徹底させることをカモフラージュする形でやっているにすぎない。即ち、学校は普遍的知識を伝達すると言いながら、そのプロセスを見てみると中産階級以上の子どものみが得をしている」というものである。学校は特定の層の人たちにのみ利益をもたらし、特定の層以外の人たちにはむしろ「不利益」になっているという議論である。
これに対し「学校の力はある」という気持ちをもった研究者がスタートさせたのが「効果のある学校」研究である。すなわち、社会的に不利な立場に置かれた人々の子どもほど、低学力傾向に陥りやすいが、そうした子どもに対しても学力向上で効果を上げている学校の存在とその学校の特徴を明らかにしていこうという研究である。
しかし1970、80年代の日本では、そういった議論はまったく話題に上らなかった。もちろん、一部の研究者や同和教育・人権教育に携わっている方々からすると同じように見えていただろうが、社会全体としては顧みられなかったのである。
その流れが変わってきたのが1990年代の中頃ではないだろうか。1990年代末から学力低下論争が起こり、2000年代に格差社会論争や「負け組」「勝ち組」といった議論が出てきて、さまざまな分野で「階層と教育の関係を考える」という教育社会学的見方が必要となってきたように感じている。
以下、こうした問題意識の高まりの中、国が関与した調査研究事業で、私が関わったものの結果を紹介していきたい。
2 文科省委託研究・第1次調査(2007年)
最初に、2007年度に行った委託研究の成果について見ていきたい。2007年度から全国学力テストが行われたが、文部科学省の側からすると、実施して回収して、素データを出し集計するまでで目一杯というところがあった。誰が見ても分析が不十分であったと言える。そこで、外部の研究者に分析の深化の委託を始めたのである。
2007年度については2つのプロジェクトが立ち上がり、その1つが耳塚寛明さん(お茶の水大学)のプロジェクトである。委託研究では、全国学力テストのデータをそのまま分析するというものではなく、そのデータの有効活用の方法を検討するという位置づけであった。やはり学力テストの結果は、生活・学習状況アンケートと重ねて分析することが必要である。そこで耳塚さんは、独自の児童への学力調査とあわせてその保護者調査、もちろん学校調査も併せて実施し分析しようとしたわけである。こういった調査を東京で実施するのは非常に珍しいが、それをパイロット的にやったのがこの第1次調査である。
その一部を私が担当し、「効果のある学校」論の視点からデータの分析を行った。パイロットスタディとして小学校40校(7自治体)が対象となっている(参照:志水宏吉「第3章 階層差を克服する学校効果」、浜野隆「第2章 家庭での環境・生活と子どもの学力」ベネッセ教育研究開発センター『教育格差の発生・解消に関する調査研究報告書』2009年3月)。
具体的には、子どもたちを「母学歴」、「収入」、「通塾」などでグルーピングして、「ある水準(基準点:テストにおいて『この程度はできてほしい』という点数)」の通過率を学校ごとに検討した。母が高卒のグループの子どもたちの通過率が何%か、かたや、母が短大以上卒のグループの子どもたちの通過率が何%かという見方をするのである。そして、「母学歴で高卒まで」「収入で500万円以下」「塾に行っていない」という子どもたちが相対的に学力面では不利なのだが、そういった子どもたちのグループの通過率を押し上げていると思われる学校を「効果のある学校」であるという見方を行った。その結果、2~3割の学校が「効果のある学校」と判定できた。
さらに、「学校背景」という視点からも考えた。我々がここ5年間くらいの取り組みで身にしみてわかったことが、「効果のある学校」かどうかというのは、学校校区の状況に非常に依存するということである。つまり、高学歴で収入が高い親が多い学校が「効果のある学校」になりやすいのである。そして、逆はまた反対であるということも明らかになっている。そこで、「学校背景1」を恵まれたタイプの学校とし、「学校背景3」をしんどいタイプの学校とした。「学校背景2」はその真ん中である。次に、学校背景と効果があるかないかを掛け合わせてみた。すると少し意外だったのが、第1次調査では、学校背景のタイプにかかわらず、ほぼ同じような割合で「効果のある学校」が出てきたのである。むしろ、「学校背景3」のタイプの学校が頑張っているのである。
なぜこのような結果が生じたのかを考えてみよう。
学校を一覧表にして眺めてみると、ある一つの自治体において、相対的に「効果のある学校」が多いことがわかった。サンプル数が少ないので、それほど顕著な違いではないかもしれないが、パッと見て「その自治体が頑張ってるな」という結果である。さらに、その自治体には「学校背景3」の学校が多く、ここが結果を引き上げたのである。これが、実は秋田県である。サンプリングを行っているので秋田全体の話ではないが、対象となっている秋田県内の学校では、親の学歴・家計収入はそんなに高くなく、また塾にもそれほど多くは通っていない。しかし、学校効果が上がっているという傾向が見られたのである。
逆に「学校背景1」の自治体を見てみると、「効果のある学校」となったのは5分の1である。これは神奈川県の都市部の学校である。しかも、地域的には落ち着いているところが対象となっている。このように見ると、両自治体の結果は対照的である。
「効果のある学校」と「効果のない学校」の子どもで、どういった項目で差が見られるかということを検討したが、やはり差は大きい。これまでの「効果のある学校」研究で出てきた結果と同じようなことが出てきている。
さらに、農村部で効果があったとされた学校と、大都市部で効果のないとされた学校を比較してみた。大都市部は親の学歴が高く、経済状況も比較的恵まれているというイメージである。逆に、農村部は、高卒の親が多く、家計収入で言うと都会のサラリーマンみたいに稼いでいるわけでもなく、塾もほとんどない。しかし、おそらく祖父母に囲まれて安定した生活を送っている子どもが相対的に多いと考えられる。
ざっと結果を見てみると、農村部の子どもたちは、必ず1時間以上勉強している。一方で大都市部の子どもたちはやらない子が多いという常識通りの結果になった。また、農村部の効果あり校では、受験学習塾(0%)、補習塾(2.0%)であるのに対し、大都市部の効果なし校では、それぞれ、35.5%、12.0%となっていることも対照的である。
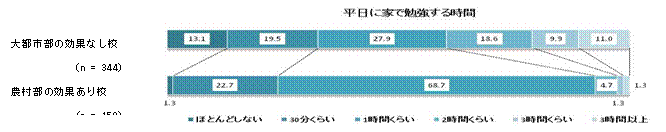
さらに、大都市部の「効果なし校」の子は、「授業の内容をわかりやすく自分でノートにまとめていない」率が高いという結果がでている。しかし、宿題以外の勉強やドリルを使っては勉強しているという結果も出た。先生や親に言われないと、あまり勉強しないという傾向も強い。逆に、「先生が気持ちをわかってくれる」「先生が私に期待をかけてくれる」「ふだん、学校で先生と話をする」などの項目で、秋田の結果の方がずっと良かったのである。
以上の分析で言えることは、次のようなことである。目新しい結論ではないが、このデータを見る限り、農村部の「効果あり校」と大都市部の「効果なし校」の間には大きな違いがある。1点目は、教師と子どもの関係が違うということである。農村部の子は教師と強い信頼関係を築けている一方、大都市部の子は、あまりコミュニケーションを取れていないようである。2点目には、いろいろな意味で、着実な学習習慣を農村部の子は押し並べて持っていることである。これに対し、大都市部の子は着実な学習習慣を持っている子と持っていない子のギャップが非常に甚だしく、持ってない子の存在が、「学力のふたこぶ目」を形成しているのだろう。
3 文科省委託研究・第2次調査(2008年)
次に、第2次調査の結果を見ていきたい。この調査は、2008年2月に、5つの政令都市から小学校20校ずつサンプリングを行い、計100校を対象として、保護者調査・学校調査を実施したものである。その結果は8月4日に公表され、文科省のホームページにも掲載されている。この調査の画期的な点は、100校の個々の保護者(学校)データと、2008年の全国学力・学習状況テストの個々の児童の結果とを結合したところにある。
(http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/045/shiryo/__icsFiles/afieldfile/2009/08/06/1282852_2.pdfを参照)。なお、保護者データと学力テスト結果を結合させるというのは画期的なことではあるが、注意すべき点もある。2006年に大阪府の学力調査で同様の方法を行ったが、保護者票の回収率が8割弱だった。そうすると、信頼性の問題が生じてくる。どういうことかと言うと、返ってこない2割ほどの保護者はどういった層なのかという問題である。推測されることは、その約2割は大抵「しんどい」方から数えた2割であり、そのまま分析をしてしまうと、一番しんどい層を置き去りにして分析を進めるということになりかねないのである。これは方法論上の問題であるが、避けがたい問題でもある。したがって、このような調査には一定程度、限界があると考えてもらいたい。
得られた主な知見の1つは、「家庭の世帯年収が高いほど子どもは高学力である」という点である。この結果は発表と同時に各地で報道された。これまで文科省は、学校別の就学援助率の高さのレベルによって学力水準が違うということを発表してきた。しかし、今回は家計にさかのぼって、経済的に豊かな家庭ほど、学力の点数が高いという結果を初めて出したということで、盛んに報道されたのである。
それでは、あまり報道はされなかった私の担当部分=「効果のある学校」について見ていきたい。
従来行ってきた児童個人を単位とした分析を今回も行った。保護者アンケートに含まれている家計の収入・親学歴などの指標をもとに、児童をグループ分けし、学力が低くなる傾向が指摘されうるグループの子どもたちに、一定の学力水準(通過率)を保っている学校を「効果のある学校」として取り出した。
さて、上記の児童個人単位のグループ分けからの「効果のある学校」の取り出しに加えて、文科省がずっと発表してきた学校の就学援助率ごとでデータから「効果のある学校」を取り出すという手法がある。ここでは、その両方の基準を満たした「効果のある学校」を取りだした。そうすると、以下のように個人ベース・学校ベースともに「効果のある学校」は20校あり、効果が出なかった学校は58校あった。
表1 2つの分析結果の比較(学校数)
|
|
就学援助率利用 |
|
|
|
効果のある学校 |
それ以外の学校 |
合計 |
保護者質問紙項目利用 |
効果のある学校 |
20 |
7 |
27 |
|
それ以外の学校 |
15 |
58 |
73 |
|
合計 |
35 |
65 |
100 |
そこで、その両方の学校の比較を様々な点で行ってみた。まず、学校質問紙の結果を検討してみた。「効果のある学校」と「効果のない学校」の間に統計的な有意差があったのは、学校質問紙の85項目中13項目であった(表2)。しかし全体を見たとき、学校のあり方、取り組み方の違いによる差異があまり出てこなかったという印象がある。学校の取り組みが効果のある学校に、直に結びつくのはなかなか難しいのかもしれない。
次に、対象となった6年生の担任の先生に、指導法などについて質問を行った結果を見てみると、「効果のある学校」と「効果のない学校」の間で、115項目中15項目で統計的に有意な差があった(表3)。授業のやり方等々で差が出ているので、やはり授業のあり方の違いは、小学生の場合、割と効果に結びつきやすいのではないだろうか。要するに、教師の指導力がクラスの子どもに跳ね返っていると考えることができるのである。
最後に、児童質問紙項目においても、違いを検討した。すると71項目中46項目、項目全体の65%にあたる項目で統計的に有意な差が見られた。要するに、児童質問紙項目に一番結果がクリアに出るということである。学校の取組み、担任の先生のやり方、子どもの生活・意識の3つを比べると、子どもの生活・意識に、「効果のある学校」かそうでないかということが直に反映されるということが明らかにされた。これは、我々の予想を大きく上回る結果であった。特に、「学校背景」下位の学校のなかで、4校存在する「効果のある学校」に通う子どもたちは、そうでない26校の子どもたちに比べると、圧倒的にポジティブな学校生活を送っている。「学習習慣」「自尊感情」「規範意識」「社会や地域への関心」「総合的な学習への関心」「国語への関心」「算数への関心」などの各領域で、「効果のある学校」の子どもたちの回答はきわめて積極的なものとなっているのである。この結果は、社会経済的要因に起因する学力差を生じさせない「学校の力」の存在を示唆するものと考えることができる。
表2 全国学力・学習状況調査の学校質問紙項目とのクロス集計結果要約 |
領域 |
学校質問紙項目 |
選択肢 |
効果の
ある学校 |
比較
対象校 |
差(効果のある
学校-比較対象校) |
p |
児童の状況 |
(11)児童は,熱意をもって勉強していると思いますか |
そのとおりだと思う |
40.0% |
15.5% |
24.5% |
* |
指導方法
・学習規律 |
(29)学習規律(私語をしない,話をしている人の方を向いて聞く,聞き手に向かって話をするなど)の維持を徹底していますか |
よく行った |
65.0% |
41.4% |
23.6% |
+ |
(31)学校や地域であいさつをするよう指導していますか |
よく行った |
90.0% |
63.8% |
26.2% |
* |
学力・学習状況の把握 |
(40)平成19年度全国学力・学習状況調査の結果を分析し,具体的な教育指導の改善に活用しましたか |
はい |
100.0% |
84.5% |
15.5% |
+ |
(42)平成19年度全国学力・学習状況調査の調査問題を授業の中で活用しましたか |
はい |
60.0% |
32.8% |
27.2% |
* |
個に応じた指導 |
(50)習熟度別の少人数による指導を行うにあたり,学習プリント等の教材として,主にどのようなものを用いましたか |
習熟度に合わせて作成した教材 |
25.0% |
3.4% |
21.6% |
* |
国語科の指導方法 |
(54)国語の指導として,書く習慣を付ける授業を行いましたか |
よく行った |
50.0% |
15.5% |
34.5% |
** |
(55)国語の指導として,様々な文章を読む習慣を付ける授業を行いましたか |
よく行った |
40.0% |
15.5% |
24.5% |
* |
(57)国語の授業では,教科担任制を実施していましたか |
実施していた |
15.0% |
1.7% |
13.3% |
* |
地域の人材・施設の活用 |
(69)PTAや地域の人が学校の諸活動にボランティアとして参加してくれますか |
よく参加してくれる |
60.0% |
37.9% |
22.1% |
+ |
教員研修 |
(88)模擬授業や事例研究など,実践的な研修を行っていますか |
よくしている |
75.0% |
46.6% |
28.4% |
* |
(91)授業研究を伴う校内研修を前年度,何回実施しましたか |
年間15回以上 |
40.0% |
24.1% |
15.9% |
+ |
「学校背景」 |
「学校背景」 |
上位 |
50.0% |
22.4% |
27.6% |
* |
※「p」はカイ二乗検定の有意確率。「**」:1%水準、「*」:5%水準、「+」:10%水準。以下同様。 |
表3 教師質問紙項目とのクロス集計結果要約
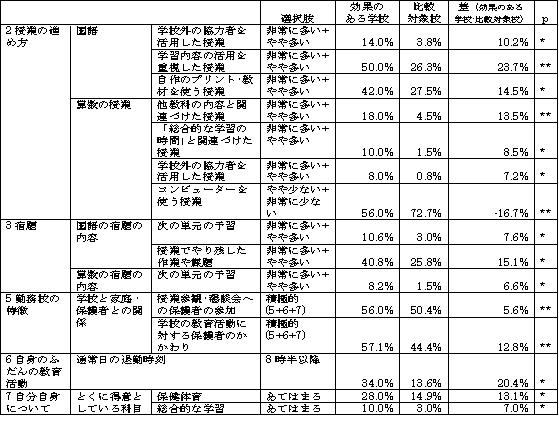
4 日本教育社会学会報告(2009年9月)
―「都鄙格差」から「つながり格差」への変化
最後に、文科省の委託研究から離れるが、私のプロジェクトの一部について見ていきたい。これは、先日(2009年9月)の日本教育社会学会で報告してきたもので、1964年の全国学力テストのデータと、2007年の全国学力テストのデータを、都道府県を単位として丹念に比較を行った。その結果が、図2である。横軸が64年の結果(小6と中3の国語、算数・数学の結果の都道府県ごとの平均値)、縦軸は07年の結果(小6と中3の国語、算数・数学ABの平均値)を示したものである。白丸の一つ一つが都道府県を表している。ただし、1964年のテストには沖縄県と福岡県が参加していないので、45都道府県となっている。
次に、2時点の学力テストのデータについてクラスター分析を行い、6つのグループを析出した。まず、何よりも驚きなのは、もっと「右肩上がり」の分布になっているのではと予想していたが、そうではなかったということである。1964年と20007年の都道府県別の結果はあまり関連していないのである。この点は、あまり論じられていないが、大きな問題だと思われる。要するに、かつて高かった府県が低くなったり、かつて低かった府県が高くなったりしているのである(参照:志水宏吉『岩波ブックレットNo.747 全国学力テスト』2009年1月、P30~31)。
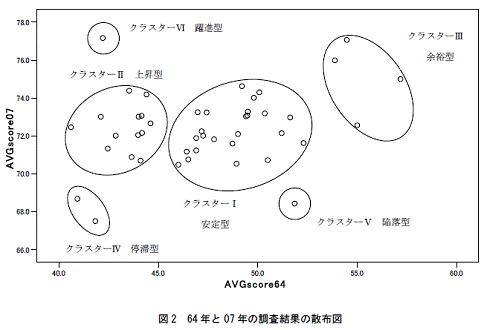
その中で「クラスターⅠ 安定型」は、昔も今も平均的というグループで、24自治体ある。「クラスターⅡ 上昇型」は、昔は低かったが今は高くなったというグループで、13自治体あり、10が東北・九州地方である。概ね、東北と九州はここに入る。「クラスターⅢ 余裕型」は、昔も今も良いというグループで、香川・愛媛・富山・福井がここに入る。「クラスターⅣ 停滞型」は、昔も今も悪いというグループで、北海道と高知である。「クラスターⅤ 陥落型」は大阪。「クラスターⅥ 躍進型」は秋田となっている。やはり秋田のみが、東北・九州グループのなかでもグンと上がっているという結果が出てきた。
さらに、1964年および2007年の結果について、30以上の社会経済指標との関連を見てみた。即ち、人口的指標(総人口・生産年齢人口割合・人口増減率・離婚率など)、経済的指標(実収入・消費支出・生活保護率・持ち家率・産業別割合など)、教育関係指標(児童生徒1人当たり教育費・高校や大学への進学率・不登校率・へき地校数など)が、その時々の学力テストのスコアにどの程度影響を与えているのかということを検討した。テスト結果と各指標相関係数を算出すると、64年と07年の結果は、重なっているようでもあり、変わっているようでもあり、ということが見て取れる。たとえば、実収入や消費支出、あるいは生活保護率といった指標は、どの教科にも今も昔も関連していると見ることができる。
しかし、非常に変わっているところもある。たとえば顕著なものとして、離婚率や持ち家率が挙げられる。64年時は、離婚率や持ち家率とテスト結果の関連はそれほど強くなかったようであるが、07年時は非常に関連が強くなっている。これを解釈すると次のように言える。昔は各都道府県の離婚率や持ち家率の格差がそれほど大きくなかったので、その要因が効いてくることは少なかったが、今はそれが広がっていて、すぐに子どもの学力に結びついているのである。
次に、多変量解析を行った結果、1964年の場合、学力と非常に関連の強い代表的な指標を2つあげると、教育娯楽費割合と高校進学率(大学進学率)であった。1964年の東京オリンピックの頃は、都道府県別の学力格差を見たときに、「子どもの教育的娯楽にいくらお金を使えるか」あるいは「高校や大学にどのくらいの人が行っているか」ということが決定的であったと言える。一言で言うと、「経済的豊かさ」とも言えるし、「都市化の進展度合い」あるいは「生活の豊かさ」と読むこともできる。いずれにしても、昔は「都鄙格差」(都会と田舎の格差)という言葉で表すことのできる状況だったのである。
一方、2007年の多変量解析の結果は、それとは対照的である。07年で非常に関連が強く、なおかつ新規の項目として上がってきたのは3つあった。まず、1番大きいのが離婚率、2番目は持ち家率、そして3番目は不登校発生率であった。これらは「発見」である。これら3つは、当然、経済的な要因に無関係ではないが、昔的な意味での豊かさかと言うと、少し違うように思われる。
この点について、もう少し深く考えてみたい。まず離婚率は、子どもの側から見ると、家庭・家族関係の安定性につながっていると考えられる。持ち家率は、昔から多少、学力に影響を及ぼしてはいたが、今はさらに影響力が強い。ちなみに、秋田や福井は持ち家率が高いが、都市部は大阪でも東京でも経済的にリッチな層もたくさんいるが、持ち家率は少ない。持ち家率が高いということは、そこに祖父母がいて、何世代も住んでおり、近所の人とも比較的親身であるということを意味するのではないだろうか。だから、持ち家率の高さは、地域の安定、人間関係のネットワークの残存を意味していると考えられるのである。最後の不登校率だが、そもそも不登校はさまざまなタイプがあり、その要因は一概には言えない。しかし、いろいろな要因を勘案してみると、不登校率が高い地域・低い地域といったときに、高い地域では「無理やったら学校に行かなくてもいい」という雰囲気がやはり流れているのではないだろうか。日本の中にも「やっぱり学校は行っておいた方がいい」という雰囲気、あるいは教師も強く働きかける地域もある。そうだとしたら、少し強引かもしれないが、不登校発生率は、その地域の子どもたちと学校の「絆の太さ・強さ」を表していると考えられないだろうか。東京あたりだと、フリースクール等々もあり、オールタナティブ・スクールを選択するという観念が広まっている。そういうところでは自ずと不登校発生率が高まるように思われる。
したがって、これら3つの指標は、家庭・学校・地域それぞれにおける人間関係の強さ・つながりの太さみたいなものを表していると言える。このことを「つながり格差」という言葉で表現したい。「つながり」のたくさんある地域の子どもは、基礎学力の水準も相対として高い。つまり、64年から07年の変化は、「都鄙格差」から「つながり格差」への変化というわけである。
学問的表現で言うと、「社会関係資本」(ソーシャル・キャピタル)という概念がある。かつて、1964年はまだ地域や家族が安定しており、日本全体に安定した社会関係資本の基盤があったのだろう。しかし個々の家庭を考えると、貧しい家庭、豊かな家庭の違いはあったはずで、それは経済資本・文化資本の格差と言える。それが安定した社会関係資本の基盤の上にポコ、ポコと現れていたゆえに、個々の家庭の経済・文化資本の格差が子どもの学力格差に結びついていたと考えることができる。
今は、日本沈没ではないが、安定した土台が残っているところもあれば沈んでいるところもあるのではないだろうか。秋田と大阪の例をあげると、秋田全体としては基盤が残存しているが、大阪はそれが揺らぎ・傾いているというふうに言えるだろう。
先日の日本教育社会学会の部会で、沖縄の低学力問題についての発表があったが、そこで「学力」と「体力」と「モラル」の関係が強いということが指摘された。モラルは規範意識と言い換えてもよいかもしれない。そして、それらの3つの原因として考えられる大きなものが「生活習慣」であり、「生活習慣」イコール「家庭の教育力」と話されていた。たしかに、生活習慣と学力・体力・モラルは相関しており、したがって「早寝、早起き、朝ごはん」をすれば、みんな良くなるという論理である。そして、その生活習慣がしっかりしているかどうかが「家庭の教育力」であり、沖縄は家庭の教育力が低くて困ったという内容である。しかし、それはやや単純すぎる図式ではないかと思う。
やはり、学力や体力や規範意識は相関性が強い。しかし、生活習慣が直接的な影響を与えていると考えるよりも、それを媒介する要因があるのではないかと考えている。それは1つは、「セルフコントロール」である。自分で自分を律することのできる身体になっているか、ということである。セルフコントロールのできる子どもは当然、生活習慣もきっちりしているし、やるべきことはやる、サボりたいけど我慢して努力する、といったことができるのである。
さらに別の見方をすると、「適応力」みたいなものになるかもしれない(「セルフコントロール」と「適応力」はイコールではないが)。「適応力」とは、学力テストなるものが行われたときに、まずは100%一生懸命やり、かつ要求されたものを考えてうまく表記できるかどうかという力である。つまり、システムから要求されたものに応えられる力である。体力テストも同様である。どうすれば良いスコアがとれるかということを考えながら行動できるか。モラルもそうである。「ゴミをちゃんと捨てなさい」と言われるから応えておいた方がいい、学校の決まりは守った方がいい、大人もそれを期待すると感じてそれに応えられる子どもは「適応力」が強いと言える。
セルフコントロールができることと、システムに適応できるかということが、どの程度同じであるのかはまだ結論に至っていない。しかし、生活習慣=家庭環境・家庭の教育力とするのは、間違っていると思う。生活習慣のもっと前に家庭環境・家庭の教育力があると思う。私の言う「セルフコントロール」や「適応力」を育む家庭と育みにくい家庭があるというわけである。「学力・体力・モラル」は学校が要求するもので、学校文化に適応している親は、そういうものを子どもにも育もうとする。しかし、そのような学校文化に馴染んでいない家庭では、別の適応力を子どもに育み、子どもが別の力を持つようになるという構造があるのではないだろうか。
5 何を考えるべきか―イギリスの動向から
以上に述べたのは、まだ「考え中」である。何しろ、「今の学力だけで本当にいいのか」という議論さえも残されている。しかし「点数学力だけでいいのか」とか「A・B(全国学力・学習状況調査)だけで本当にいいのか。もっと別のものが必要では」という議論もあるにはあるのだが、ここではひとまず置いておきたい。前提として、学校に行っている子どもたちには、AとBの力を「そこそこ」つけてやらないといけないと思う。
かつて同和教育の中で「受験の学力/解放の学力」という言葉を使って、「受験の学力ではなく解放の学力こそが必要だ」という議論があった。しかし私が思うに、学力は1つのもので、表裏がある。「受験の学力はいらなくて、解放の学力だけでいい」というのはおかしい。1つの学力が受験にも解放にも使える。その土台となる学力をまずつけようということである。
そういう観点から考えたときに、学力の調査研究を始めて7年くらいになるが、この7年間にいわゆる格差が広がっていると思う。学力状況が「ふたこぶ」から「みこぶ」になり、さらにそれが台形になる。その結果が、文科省の調査結果なども含めてどんどん出てきているが、そういった問題を考える際に参考になるのがイギリスの例ではないだろうか。
イギリスでは、1980年代に「のんびり」やっていたので国が傾いた。そこにサッチャーという女性が出てきて国を建て直そうとした。弱肉強食・自由競争の教育界を作り出そうとし、血が流れても全体として力がアップすればよいというやり方であった。その後、5年、10年経って、イギリスは浮上し、そして90年代半ばにはブレア政権=労働党政権が誕生した。ブレアは、あんまり血が流れるのは良くないということで、「第3の道」と言われるような修正路線、つまり、底辺層のしんどいところは支援しないといけない、そのうえで適正に競争を、という政策をとった。その政策が今日まで続いている。
現在の新しい施策に、「シュア・スタート」というものがある。それは、しんどい地域の幼児教育に対するテコ入れである。かつて日本の同和地区に保育所を作ったことと形は似ている。朝ごはんを食べさせるといったことも行われている。それによって、小学校1年生へのギャップをなくそうとしているのである。
対照的なのがフィンランドである。今年の3月に訪問したが、その折「ノーテスト、ノーインスペクションである」と関係者が誇らしげに言っていた。ナショナルテストは行わず、査察(学校評価)も行わなず、現場・教師を信頼しているという話を聞くことができた。
現在、教育の世界では、新自由主義的に国家主導でやるのか、昔ながらの社会民主主義的に(フィンランドでそうは言わないが)現場への信頼重視でやるのかといった二大潮流のようなものが存在している。日本の現状を見た場合、どちらの道を歩もうとしているのかという大きな争点がある。さらに政策面で非常に立ち遅れているが、「面」のサポートである。奨学金を出したり、子ども手当てを出したりという個人に対するサポートは、必要である。しかし、日本の社会関係資本を考えると、個々の家計のみにサポートしても、それは消費されて新たなものにつながっていかない可能性もある。「面」のサポートというのは、地域のグループ、あるいは学校がグループになって、そこでの取り組みを行政がサポートするというものである。こういった施策は、イギリスで「普通に」なされていることであり、日本においても参考にできる点が多いと考える。 |