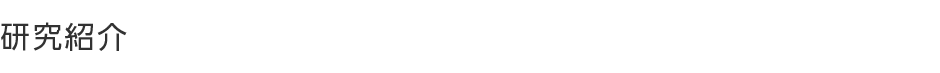

当研究所では、以下の研究部門をもうけ、正会員である研究者・実践者とともに運動・実践に資する調査研究活動を進めています。
公開研究会の開催
各研究部門ではテーマごとに研究会を開催し、随時公開講座を開催しています。
研究成果の発表
研究部門では、研究の成果を紀要『部落解放研究』や『部落解放・人権研究報告書』に発表しています。
また、投稿論文も受け付けています。
受託による調査研究
自治体や各種団体・組織、企業等から、人権課題にかかわる意識調査・実態調査等の委託を受け、調査研究の設計・実施、結果の集計・分析等を行なっています。
科学研究費助成による調査研究
2011年度より科研費による助成を受け、調査研究事業を実施しています。
※年度ごとの調査研究の詳細はこちらの「事業報告(調査・研究部)」をご覧ください。

第一研究部門:「部落史の調査研究」
部落史や被差別民の歴史等について史料調査等をもとに進めています。
 廣岡浄進
廣岡浄進
第二研究部門:「性差別構造の調査研究」
とりわけ被差別マイノリティを対象として、「ジェンダー」「セクシャリティ」等の観点から、複合的・重層的な性質を持つ性差別構造について調査研究を進めています。
 谷口真由美
谷口真由美
第三研究部門:「人権教育・啓発の調査研究」
識字教育・同和教育の実践と実績をふまえて、「人権教育」「成人基礎教育」「ソーシャルワーク」といった観点も組み入れつつ、 学校教育・社会教育・地域教育における人権教育・啓発のあり方について調査研究を進めています。
 森実
森実
第四研究部門:「差別禁止法の調査研究」
差別禁止法の制定をめざして、国内外の差別禁止法に関する学習、立法事実(差別事件・差別実態等)の収集、差別事件の判例分析、被差別マイノリティのネットワークづくり等をとおした調査研究を進めています。
 内田博文
内田博文
第五研究部門:「社会的排除の調査研究」
被差別部落が抱える困難と社会全体に広がる困難(格差・貧困問題等)の相違点を分析・考察し、運動・実践との関連から生活困窮者自立支援法や各種貧困対策関連法の可能性と課題について調査研究を進めています。
 福原宏幸
福原宏幸
第六研究部門:「部落差別の調査研究」
2016年12月の「部落差別の解消の推進に関する法律」の施行をふまえ、現在も残る部落差別・部落問題に関する調査研究を進める部門を立ち上げました。「部落差別事件の集約分析」「部落差別体験の聞き取り」「全国自治体を対象とした同和行政の実態調査」「地方公共団体が実施した既存調査の集約分析」「インターネット上の部落差別の実態調査」「行政データを活用した実態調査」「地域福祉課題解決にむけた法律・制度・実践の調査研究」等に、 部落解放同盟中央本部、各都府県連合会、関係諸団体と連携・協働しながら取り組みます。
 北口末広
北口末広